
近年、音楽配信や動画配信をおこなうサブスクなど、「サブスク」という言葉を耳にする機会が多くなってきました。
サブスクとはサブスクリプション(ビジネス)の略で、基本的には会員登録制のサービスで、一定の期間に対して一定の金額を支払うビジネスモデルのことを指します。
今までもこのようなサービスは一定数ありましたが、ジャンルに捉われないさまざまなサービスが生み出され、より一層サブスクリプションビジネスが注目されるようになってきました。
月額、年額などのサービスを導入する際は、一定のサイクルで継続して課金を続ける決済システムが必要不可欠です。
この「継続課金システム」を導入するためには決済代行サービスを利用するのが一般的ですが、ビジネスモデルや商品・サービスによって、どの代行サービスを利用すべきか検討する必要があります。
今回は、継続課金システムを導入するにあたって気になる、
- 継続課金・都度課金の仕組みと違い
- サブスクリプションビジネスのメリット
- 継続課金方式でPAY.JPが選ばれる理由
についてご紹介していきます。
継続課金とは?2種類の課金方式とその違い
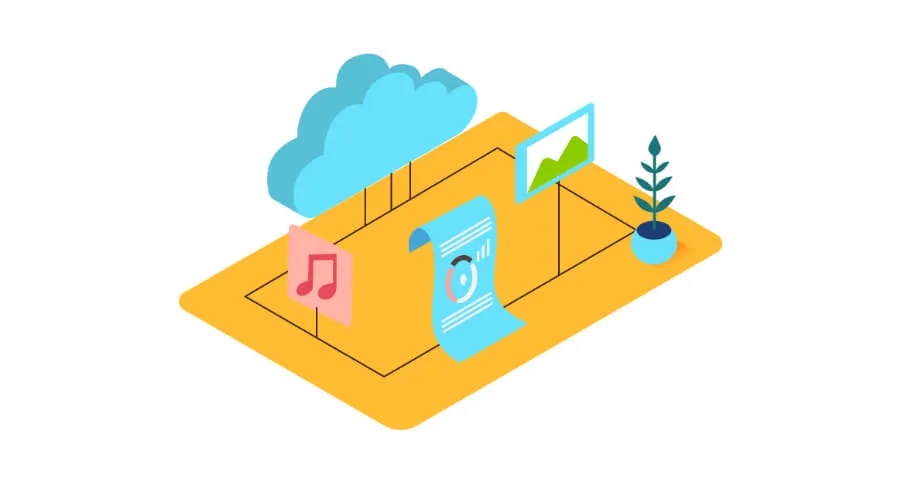
まず、商品やサービスを販売する際の課金方式は、次の2つに分けられます。
- 継続課金(定期課金)
- 都度課金
継続課金(定期課金)とは?任意の期間・金額で継続的に課金
継続課金とは、お客様がサービスを退会されない限り半永続的に課金が発生する課金方式のことです。
中長期的に売上が発生しますので、主にサブスクリプション型のビジネスモデルの課金方式として用いられています。
1ヶ月ごとの利用料金を毎月支払うような月額制のサービスも、継続課金にあたります。
月額制の動画配信サービスやフィットネスクラブの月会費などがまさに月額制の継続課金です。
金額が定額ではなく、一定期間に利用した料金分だけ課金をするようなサービスも継続課金に含まれますので、「一定のサイクルで課金が発生する方式」と考えるとわかりやすいかもしれません。
なお、継続課金は「定期課金」と呼ばれることもあります。
都度課金とは?サービスの購入ごとに課金
都度課金とは、商品やサービスを購入するごとに料金が発生する課金方式のことを言います。いわゆる「買い切り」のことで、日常的に物を買う際はこちらがオーソドックスです。
例えば、ソフトウェアのライセンス購入方法が買い切りと月額制2つあった場合、下記のようになります。
- 一度購入すれば半永久的に利用できる:購入時のみ課金→都度課金
- 毎月ライセンス利用料を支払う:毎月一定額を課金→継続課金
物販やスポットでのサービス提供であれば、実店舗だけでなく、ECサイトなどのオンラインでもこの都度課金を採用していることがほとんどです。
継続課金とは違って、中長期的に課金が発生するものではありませんので、物を購入する側としては購入のハードルが低いといったメリットがあります。
サブスクリプションビジネスの3つのメリット

継続課金は、主にサブスクリプション型のビジネスモデルの決済方式として採用されています。
サブスクリプションビジネスのメリットを3つご紹介します。
- 継続的な売り上げが見込め、中長期の見通しが立てやすい
- 消費者のデータを集めやすく、サービス改善に活かせる
- 顧客との継続的な関係が作れる
①継続的な売り上げが見込め、長期的な見通しが立てやすい
売り切り型の商品やサービスの場合、特に中長期の見通しを立てるには前年度実績値などから予測するといったことが必要になり、試算が非常に困難です。
顧客との関係性がサブスクリプションに比べると薄いため、リピート率の予測や顧客分析も一苦労です。
試算した結果から実績が乖離し、計画の見直しが必要となることも多々あります。
一方でサブスクリプションの場合は、利用者が解約しない限りは一定金額の売り上げが発生するため、中長期での利益の見通しが立てやすいのが特徴です。
予測を立てる際も、見込みの新規獲得者数を試算し、それに対して利用料金をかけるといったものになるため、売り切り型に比べると比較的計画が立てやすいといわれています。
その分、見込み顧客の囲い込みや、解約防止などどのように顧客との関係性を維持していくか、長期的に利用してもらうために適切なサイクルでサービスを改善していけるかが非常に重要になってきます。
②消費者のデータを集めやすく、サービス改善に活かせる
サブスクリプションは基本的に会員登録をして利用するサービスが多く、消費者のデータを集めやすいため、顧客動向をサービスの改善に活かすことができます。
顧客が継続的にサービスを利用してくれるため、サービスの利用状況を細かく見ることが可能です。
たとえば毎月定額制の動画配信サービスの場合であれば、ユーザーの属性に応じて好みの動画がわかり、同じような属性のユーザーへ関連動画をおすすめに表示できます。
そのほかにも、どのようなユーザーにどの動画がよく見られていて、どのタイミングで離脱する傾向にあるのかなどが日々集計されますので、新しいデータをもとに各コンテンツを改良・充実させることも可能です。
顧客とのタッチポイントが日常的に続くという利点を生かし、サービス改善に繋げていけることこそ、サブスクリプションの最大のメリットといえます。
③顧客との継続的な関係が作れる
サブスクリプションビジネス=定額サービス・月額サービス、といったイメージが強いですが、本来は顧客との継続的な関係性に本質があるビジネスモデルです。
顧客と繋がり続けることには大きな意味があります。
②でも記述したように、顧客分析をしてサービスの改善に繋げることができ、それが結果として新規ユーザーの獲得や解約防止にもつながるためです。
単発のタッチポイントではなく、初回購入後も顧客との接点が続くというのはサブスクリプションビジネスにおいて非常に重要なポイントとなります。
また、利用を継続してもらうためには、ある程度金額を少額に設定しておくこともポイントです。
継続的に課金が発生しても、お客様にとってその金額が少額であれば大きな負担にはなりません。
少額のサブスクリプションサービスは、お客様の負担が少ないため、継続率を上げやすいといった傾向にあります。
また最近では、初月無料などトライアル期間を設定し初回の購入ハードルを出来るだけ低くしているサービスも多いです。
継続課金システムは決済代行サービスの利用がおすすめ

オンラインで継続課金方式を採用する場合、クレジットカード決済やキャリア決済、口座振替などの継続課金にあった決済方法を準備する必要があります。
しかし、各種決済システムを個人や中小企業が独自で導入するのは困難です。
たとえば、クレジットカード決済を導入するためには、カードブランドごとのセキュリティ基準を満たさなければいけませんし、カード会社ごとに異なる入金サイクルにも対応して売上管理していく必要があります。
一方で、課金システムの決済代行会社に依頼すれば、面倒なカード会社との契約やカード情報の保持を代行してもらえ、売上管理もシンプルなものになります。
決済代行会社によってはクレジットカード決済だけではなく、コンビニ決済や銀行振込、キャリア決済などを一度に導入することも可能です。
そのため、継続課金システムの導入をお考えの方には、決済代行サービスの利用をおすすめします。
継続課金システムの決済代行サービスを比較!PAY.JPが選ばれる理由
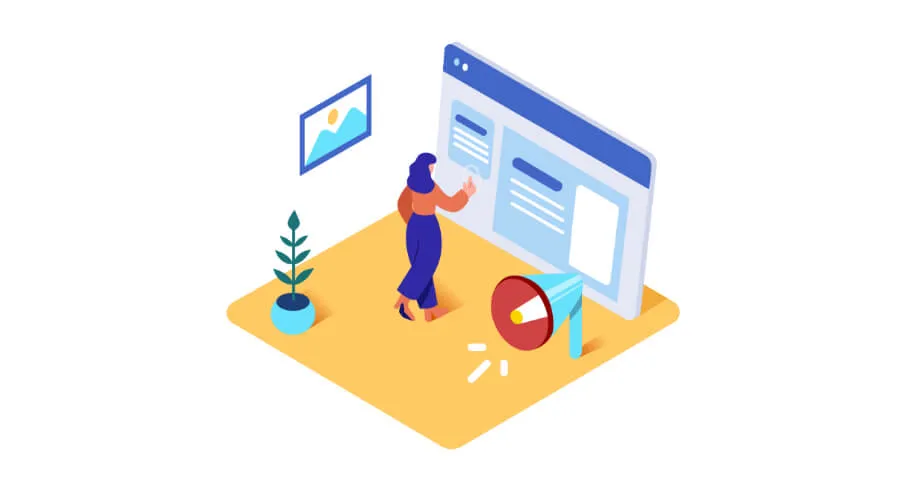
継続課金システムの決済代行サービスにはさまざまなものがあります。
弊社が提供している「PAY.JP」もその1つで、定期課金の仕組みを提供しております。
PAY.JPは初めて決済代行サービスを導入される事業者様をはじめ、みなさまに簡単に導入いただけるような料金設定やサービス内容を心がけています。
【PAY.JPと一般的な決済代行サービスの違い】
| PAY.JP | 一般的な決済代行サービス | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 無料 | 無料 |
| 月額費用 | 無料 (プロプランのみ10,000円) | 3,000円~10,000円 |
| 決済手数料 | ・ベーシックプラン:3.0%〜3.6% ・プロプラン、seed:2.59%〜3.3%・Travel、NPO:1.5%〜3.6% | 3%~10% |
| トランザクション費用 | 無料 | 数円〜数10円/回 |
| 対応主要カードブランド | ・VISA ・Mastercard ・JCB ・AmericanExpress ・Diners Club ・Discover | ・VISA ・Mastercard ・JCB ・AmericanExpress ・Diners Club ・Discover |
| 審査・導入日数 | ・VISA、Mastercard:3〜4営業日程度 ・それ以外:1ヶ月程度 | 3週間〜2ヶ月程度 |
| 継続課金のトライアル期間 | 自由に指定可能 | トライアル期間の指定不可 |
| 継続課金の決済指定日 | 自由に指定可能 | 自由に指定可能 |
| 継続課金の自動更新 | あり | なし |
ここからは、継続課金システムとして「PAY.JP」が選ばれる主な3つの要素についてご紹介していきます。
簡単に実装できて学習コストを抑えられる
PAY.JPは決済システムを簡単に実装できますので、学習コストを抑えることができます。
通常、決済代行サービスを利用するためには各社製品の使い方やシステム構築の方法まで学習しなければなりません。
システムが複雑であると学習コストが大きくかかり、システム導入に時間がかかってしまったり、システム導入後も売上管理などで手間がかかったります。
とくにベンチャー企業やスタートアップ企業の方については、開発費用の面からも学習コストの低いサービスが好ましいでしょう。
PAY.JPは必要な機能だけを集約したシンプルなシステムとなっておりますので、学習コストを抑えてシステムの実装から利用までスムーズに行っていただけます。
手数料が低くて個人事業主でも導入しやすい
PAY.JPは手数料が低いため、個人事業主の方でも決済システムを導入しやすいです。
PAY.JPのプラン別の決済手数料は次の通りです。
| ベーシックプラン | 3.0%〜3.6% |
|---|---|
| プロプラン、PAY.JP seed | 2.59%〜3.3% |
| PAY.JP Travel、PAY.JP NPO | 1.5%〜3.6% |
ベーシックプランのうち、VISAやMastercardでは3.0%、JCBやAmerican Expressでは3.6%としております。
一般的なクレジットカード決済の手数料は3%~10%とされていますので、決済手数料は比較的低い水準ではないでしょうか。
また初期費用や導入費用、トランザクション費用は無料です。
そのため個人事業主をはじめ、小規模の事業を営む事業者様にとっても導入いただきやすいと思います。
課金システム実装までのスピードが早い
「今すぐ継続課金システムを実装したい」
「スピード感を持ってシステムを実装されたい」
といった事業者様にPAY.JPはお選びいただいております。
PAY.JPはアカウント登録後すぐにテスト環境をご利用いただけるようになります。本番環境でカード決済を実装するためにはカード会社の審査が必要ですが、その審査を待っている間にも開発を進めていただくことが可能です。
スピーディに開発できたとのお声を多く頂戴しておりますので、、すぐに継続課金を実装したいといった方はぜひPAY.JPをご検討ください。
業界最低水準の手数料(2.59%~)で簡単導入できる決済サービス
PAY.JPの定期課金でできること

PAY.JPの定期課金(継続課金)でできることをご紹介します。
- 年1回、月1回の請求サイクルを導入
- トライアル期間の設定
年1回、月1回の請求サイクルの導入
PAY.JPでは年1回もしくは月1回の請求サイクルを導入いただけます。
サブスクリプション型のサービスは月額制が多いため、多くの事業者様でPAY.JPをご利用いただけるかと思います。
課金日の指定も可能で、毎月月末に課金されるようにする、初回登録日を基準として以降は毎月その該当日に課金をするといったこともできます。
また初回登録日から次回課金日までの日割り金額を計算し、登録時点で課金するといったことも可能です。
このように課金間隔や課金日を柔軟にカスタマイズできますので、さまざまなビジネスモデルに対応可能です。
トライアル期間の設定
PAY.JPの定期課金ではトライアル期間を設定することができます。
たとえば30日間のトライアルを設定すれば、サービスを利用し始めた日から30日後に実際の課金が行われ、その日を基準として定期課金を実装できます。
そのほか、すでに定期課金が行われている場合でも任意の無料期間を設けて、課金のタイミングを調整するといったことも可能です。
サービスの無料期間をうまく利用して、お客様の流入増加を目指しましょう。
組み合わせることでこんな課金サイクルが実現できる!
PAY.JPでできることを組み合わせた実例として、以下のようなものがあります。
- オンラインサロンの月額料金
- プログラミング教室の月額利用料
- フィットネスジムの月額利用料
- サブスクリプション型モデルのWebサービス
- ファンクラブの月会費
課金サイクルとしては、30日の無料期間の後に月1回の定期的に課金が発生するものや、月途中での入会者は初月日割りで課金が発生するものなどさまざまです。
PAY.JPを利用すれば、ビジネスモデルやサービスに応じてあらゆる課金サイクルを構築いただけます。
継続課金の実装をお考えの事業者様はPAY.JPの利用をご検討ください。
まとめ
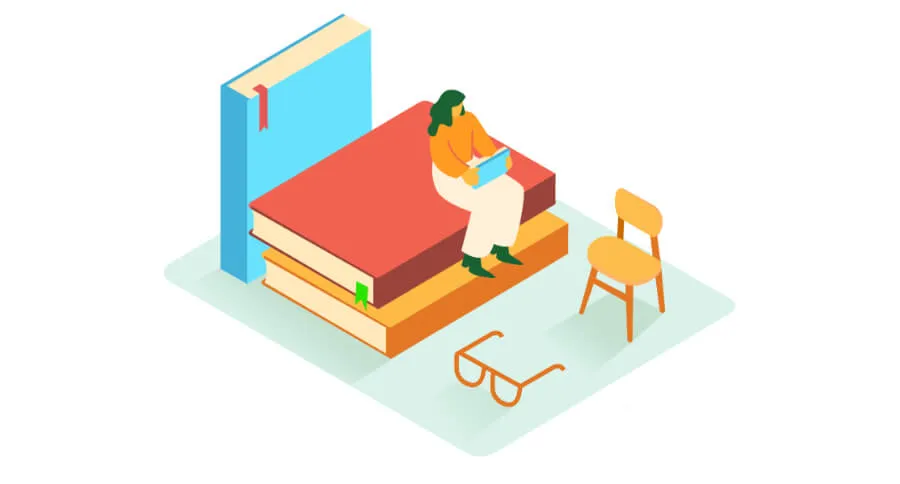
最後に、本記事の内容をまとめます。
- 継続課金(定期課金)は任意の期間と金額で課金を発生させる課金方式
- 継続課金はサブスクリプション型のビジネスモデルに最適
- 継続課金システムの導入には決済代行サービスの利用がおすすめ
- PAY.JPは簡易的に導入でき、定期課金の実装もできる
各決済代行サービスの中でもPAY.JPは学習コストを抑えられ、システムの実装スピードも早いことが特徴です。
ベンチャー企業やスタートアップ企業などスピード感を必要とする事業者をはじめ、個人事業主なども含めた小規模の事業を営む方はぜひPAY.JPをご検討いただければと思います。